
test202504173
吉田和行 2025/04/24
7/5(土)
2025年
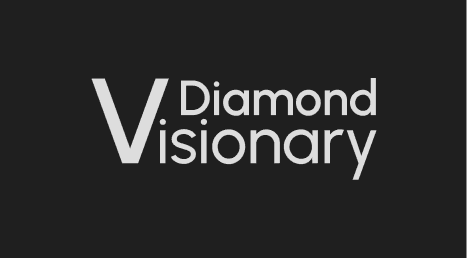
ビジョナリー編集部 2024/09/03
集団浅慮(グループシンク)とは集団で合意形成を行う際に、個人で考えたアイデアよりも質が劣り、不合理な結論に至ってしまう現象を指します。アメリカの心理学者アーヴィング・ジャニスが提唱したこの概念は、特に組織やチームでの意思決定において重要な問題となります。集団浅慮は、集団の凝集性が高まると発生しやすく、同調圧力や閉鎖的な環境がその要因となります。
集団浅慮の具体例として、以下の事例が挙げられます。
1961年、アメリカのケネディ政権がキューバのカストロ政権を倒すために行った侵攻作戦。反対意見が出にくい環境が作られ、作戦は大失敗に終わりました。
1986年、NASAのスペースシャトル「チャレンジャー号」が打ち上げ直後に爆発。現場の技術者たちの反対意見が無視され、打ち上げが強行されました。
集団浅慮が発生すると、以下のようなデメリットが生じます。
不合理な意思決定
集団としての合意が優先されるため、合理的な判断ができなくなります。
リスクの過小評価
集団としての自信が過度に高まり、リスクを軽視する傾向があります。
多様な意見の排除
異なる意見が出にくくなり、結果として多様な視点が欠如します。
倫理観の欠如
集団の結論が道徳的に正しいとされ、倫理的な問題が無視されることがあります。
集団浅慮に陥った場合、以下のような症状が見られます。
集団浅慮が発生する原因として、以下の要因が挙げられます。
集団凝集性の高さ
集団の結束力が強いほど、多様な意見が出にくくなります。
閉鎖的な環境
外部からの情報が遮断され、内部の意見だけで意思決定が行われる。
リーダーの権力
リーダーや特定の人物の意見が強く、他の意見が排除される。
過度なストレス
ノルマやトラブル対応など、ストレスが高い状況で短絡的な意思決定が行われる。
利害関係の発生
意思決定に利害が絡むと、個人の利益が優先される。
集団浅慮を避けるためには、以下の対策が有効です。
リーダーの意識改革
リーダーは中立の立場を守り、意見を引き出す役割に徹する。
意見しやすい環境作り
異なる意見を受け入れる雰囲気を作り、批判的な意見も尊重する。
グループを小さく分ける
小グループでの議論を行い、多様な意見を引き出す。
外部の意見を取り入れる
外部の専門家や第三者の意見を積極的に取り入れる。
批判役を用意して議論する
批判的な意見を述べる役割を設け、反対意見を引き出す。
集団浅慮は、組織やチームでの意思決定において重大な問題となる現象です。適切な対策を講じることで、集団浅慮を回避し、より合理的で多様な視点を取り入れた意思決定を行うことができます。今回紹介した対策を参考に、集団浅慮の罠から脱出し、健全な組織作りを目指しましょう。